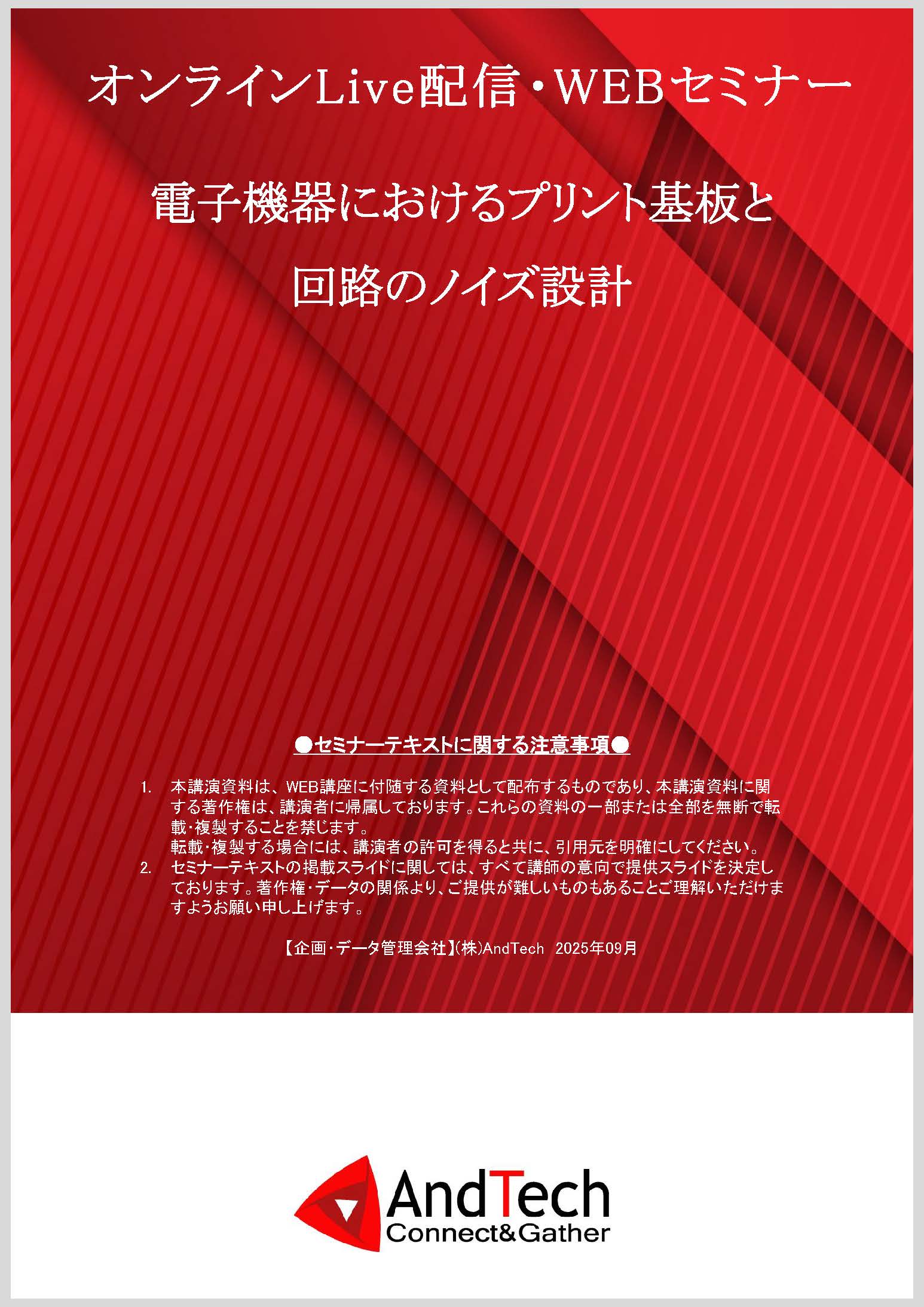電子機器におけるプリント基板と回路のノイズ設計
■本テキストの主題および状況(講師より)
★身の回りから工場の設備に至るまで、様々な電子機器がスイッチング電源と高速デジタル回路で構成されてきています。これらに共通する規格適合上の難題といえば、何といっても「ノイズ」です。
★プリント基板は、無頓着に設計すれば、電源やクロックがノイズをまき散らすことになります。逆に、外来ノイズに反応して誤動作したりするトラブルに追われることもあります。さらに、開発の最終段階でこれらを試験するEMCは製品試験の中でも、困難なものです。
★ノイズ問題は電磁気の知識やアナログ的な手法を要するのでとっつきにくく、アナログ回路を学ぶ機会が少なくなった昨今、ノイズを単なる厄介者として扱うしか、手がない状況も見られます。
■注目ポイント
★回路や基板設計におけるノイズの問題がなぜ起きるのか、回路設計段階での対策部品の使い方、基板設計段階での部品配置やパターンニングなどのノウハウを解説・紹介!
★ノイズに強い回路・プリント基板設計が可能になることを目指す講座!
★「開発段階でのノイズ対策をどう考えればよいか」ということを中心に(極力数式を使わず)伝送線路やアンテナといったノイズに関わる回路の考え方を解説!
★設計段階からノイズの発生と拾い込みを防止するため「何故そうするか」の理由と共に対策について解説!
執筆者
【講師】
倉西技術士事務所 所長 倉西 英明 氏
目次
【主旨】
身の回りから工場の設備に至るまで、様々な電子機器がスイッチング電源と高速デジタル回路で構成されてきています。これらに共通する規格適合上の難題といえば、何といっても「ノイズ」です。
中でも、その要であるプリント基板は、無頓着に設計すれば、電源やクロックがノイズをまき散らすことになります。逆に、外来ノイズに反応して誤動作したりするトラブルに追われることもあります。さらに、開発の最終段階でこれらを試験するEMCは製品試験の中でも、困難なものです。
一方、ノイズ問題は電磁気の知識やアナログ的な手法を要するのでとっつきにくく、アナログ回路を学ぶ機会が少なくなった昨今、ノイズを単なる厄介者として扱うしか、手がない状況も見られます。
そこで、本テキストでは、単なるノウハウの羅列ではなく、ノイズの物理現象や性質から始めて、「何故そう設計するか」を理解した上で対策法を学びます。
【プログラム】
1 ノイズの基礎
1.1 ノイズとは何か
1.1.1 基板と電磁エネルギーの出入り
1.1.2 ノイズの定義
1.1.3 電子回路の干渉とEMC
1.1.4 ノイズの時間的特性
1.1.5 ノイズの伝達経路
1.2 ノイズの物理
1.2.1 物理の話の前に
1.2.2 ノイズと物理法則
1.2.3 交流の基礎知識
1.2.4 交流とスペクトル
1.2.5 見えないLとC
1.2.6 共振現象
1.2.7 電磁波の発生とアンテナ
2 プリント基板のノイズ設計
2.1 プリント配線の基礎
2.1.1 基板とノイズ
2.1.2 基板パターンと伝送線路
2.1.3 信号とリターン経路
2.1.4 電源層・GND層
2.1.5 ノイズを考慮した層構成
2.2 回路設計の要点
2.2.1 回路構成の設計
2.2.2 能動部品の選択
2.2.3 受動部品の選択
2.2.4 ノイズ対策部品の選択
2.3 部品配置の要点
2.3.1 パワエレ回路の配置
2.3.2 高速部品の配置
2.3.3 対策部品の配置
2.3.4 アナログ回路の配置
2.3.5 発熱部品の配置
2.4 配線設計の要点
2.4.1 クロックの配線
2.4.2 電源周りの配線
2.4.3 高速信号の配線
2.4.4 外部接続周りの配線
2.4.5 アナログ回路周りの配線
3 ノイズ対策の実際
3.1 基板特有の事情
3.1.1 市販ユニット・外部設計品
3.1.2 基板製作の流れ
3.1.3 指示書類作成のカギ
3.1.4 基板設計者との意思疎通
3.2 効率的なノイズ対策
3.2.1 素早く原因を掴むコツ
3.2.2 再現性を確保する手法
【キーワード】
ノイズ プリント基板 回路 対策 リターン電流 伝送線路 ノウハウ 部品
【ポイント】
プリント基板で対策を講じておかないと、後からノイズ対策を行うのは非常に困難です。このテキストでは、設計段階からノイズの発生と拾い込みを防止するため、「何故そうするか」の理由と共に対策について述べて行きます。
【習得できる知識】
1)回路や基板設計におけるノイズの問題がなぜ起きるのかが分かる
2)回路設計段階での、対策部品の使い方(適材適所)が分かる
3)基板設計段階での、部品配置やパターンニングなどのノウハウが得られる