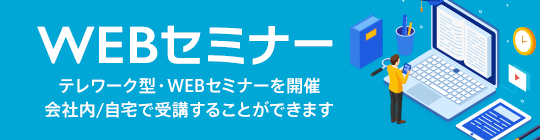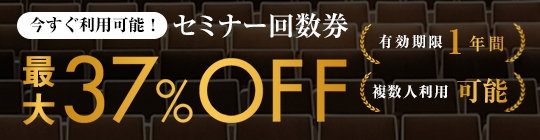セミナー検索結果 10件中
※開催予定日に変更点がございます。(7月25日(金)から24日(木)に変更いたしました。)
★2025年7月24日会場運営セミナー。三井化学株式会社 中川氏、が【吸音・遮音の基礎(メカニズム)および評価方法と音響メタマテリアルへの展開】について解説する講座です。
■注目ポイント
★吸音・遮音の基本的な考え方、多孔質材料の吸音メカニズム、吸音性能・遮音性能の正しい評価方法を解説!
★2025年7月25日WEBでオンライン開講。足利大学 西 剛伺 氏、株式会社レゾナック 小野 雄大 氏、JNC石油化学株式会社 藤原 武 氏の3名がパワー半導体の発熱対策と高放熱材料の開発・応用展開について解説する講座です。
■注目ポイント
★半導体の構造や発熱メカニズムから、伝熱経路の種類と主な放熱機構、温度予測手法や伝熱経路のボトルネック把握手法等について解説!
★レゾナックの取り組みや事例として焼結銅ペーストの性能と適用技術について紹介!
★JNCが開発している重合性液晶化合物を高放熱材料に用いた実例、およびその低誘電率化について解説!
★2025年7月25日WEBでオンライン開講。福岡大学 八尾 滋 氏がプラスチックの自己再生能力を基盤とした環境配慮設計・高度資源循環システムについて解説する講座です。
■注目ポイント
★高分子が持つ自己再生能力に注目した物理劣化・物理再生理論について基礎から学び、新たな視点での環境配慮設計やマテリアルリサイクルでの高度物性再生プロセスを通じた資源循環システムの構築の具体的な方針について解説!
★2025年7月25日WEBオンライン開講。信州大学 繊維科学研究所 大越 豊 氏から、高分子延伸による強度制御 ~延伸繊維・フィルムの構造と物性~のテーマについて解説する講座です。
■本講座の注目ポイント
★延伸に伴う構造変化が得られる繊維やフィルムの物性、特に強度におよぼす影響に関して、延伸工程や強度発現メカニズムの概説から最新の研究成果までを交えて総合的に解説。構造としては分子配向、配向結晶化、および階層構造形成に注目し、強度以外にも伸度とヤング率、熱収縮、および複屈折にも言及する。
★2025年7月28日WEBでオンライン開講。 大阪大学 宇山 浩 氏、理化学研究所 竹中 康将 氏、群馬大学 粕谷 健一 氏の3名が、海洋生分解性バイオプラスチック最新技術 ~生分解性プラスチックの基礎、デンプンを基盤とした創製、包装・農業用途向け高ガスバリア性素材、微生物を集めてプラスチックを食べさせる技術~ について解説する講座です。
■本講座の注目ポイント
海洋生分解性プラスチックの最新技術を紹介。自然由来素材を高度に組み合わせた生分解性と機能性を両立させた新しい材料設計、高ガスバリア性を併せ持つ包装・農業用途向け新規海洋生分解性プラスチック、そして、生分解性プラスチックに微生物誘引物質を混ぜることでプラスチック周辺に微生物を集め、プラスチックを無機化させる新技術等、社会実装に向け、その展望までを解説。バイオマス素材の社会的意義や未来の持続可能なものづくりに貢献するための講演を行います。
※開催予定日に変更点がございます。
★2025年7月29日WEBでオンライン開講。ソフトマターデザインラボ合同会社 佐々木氏(元東亞合成株式会社)が、レオロジー中級講座~高分子材料の本質的理解に役立つ動的線形粘弾性の仕組み・理論を伝授~について解説する講座です。
■注目ポイント
★高機能・高性能な高分子材料の設計開発に役立つ動的線形粘弾性の測定原理について基礎的事項から説明!
■関連講座のご案内
本講座と関連した初級講座の開催を2025年5月30日(金)に予定しております。参照ページは下記タイトルをクリック。
★2025年7月29日WEBでオンライン開講。ビックケミー・ジャパン株式会社 谷氏が、【工業用添加剤の基礎と選定スキルおよび効果的な活用法の習得に向けたポイント】について解説する講座です。
■注目ポイント
★化学業界で20年以上の経験を持つ講師が実例を交えながら添加剤選定の勘所を体系的に解説!
★2025年7月31日WEBでオンライン開講。関西大学 工藤氏が、【高屈折率材料の基礎・原理と分子設計の指針および物理的特性の評価方法】について解説する講座です。
■注目ポイント
★高屈折率材料の屈折の原理、応用する用途ごとの適切な屈折率測定方法、アッベ数と屈折率の関係、ケイ素元素を有する高密度なポリマーなどの特殊構造高分子と物理的特性、テルルポリマーの合成と屈折率特性等豊富なプログラムでその基礎から分子設計、屈折率測定法や選定、応用技術まで解説!
★2025年7月31日WEBでオンライン開講。 徳島大学 上田先生、芝浦工業大学 田邉先生、桐蔭横浜大学 杉本先生がそれぞれインフラ診断高度化のための非破壊検査の最新技術と測定評価手法について、近赤外光およびミリ波・テラヘルツ波、 非接触音響探査法などを使用した検査技術につき、解説する講座です。
■注目ポイント
★注目の非接触音響探査(NCAI)法の概要として、橋梁床版(高さ30mを超える高架橋),地下空洞天井部における吹付コンクリート(離隔25m)および飛行中のドローンからの音波照射加振を用いたタイル外壁などの探査結果例に加え、現在検討が行われている移動計測なども含めたNCAI法の最新動向についても紹介!
★また近赤外光やテラヘルツ波を利用した検査手法はコンクリート中の塩化物イオン濃度や,水分,中性化など,コンクリート中の鋼材腐食や様々の劣化を引き起こす劣化因子を効率よく検出できる可能性がある。その研究について学ぶことができる!
★2025年8月4日オンライン開講。【(元)村田製作所/(現)和田技術士事務所・代表:和田氏】電子セラミックスの専門家が、積層セラミックコンデンサ(MLCC)の構造から製造プロセス、信頼性評価や技術展望について解説する講座です。
■本講座の注目ポイント講演日以降でもアーカイブ視聴可能です(8/5~8/22の期間)
MLCC製造プロセスの全容(誘電体、スラリー、電極設計)について学習できる講座です。
①BTを中心に誘電体材料について解説します!
①セラミックスラリー作成から内部電極ペースト、電極印刷、剥離・積層、脱バインダー/焼成工程ついてのポイントを解説します!
②小型・大容量化や車載に向けた高圧、高温化など、今後の技術展望についても紹介します!