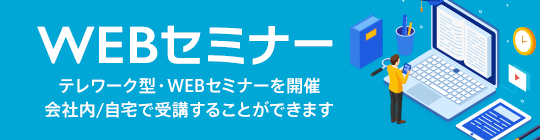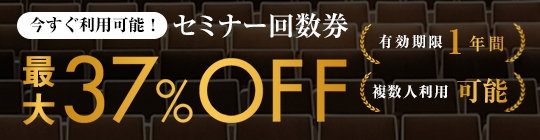セミナー検索結果 10件中
★2026年2月24日WEBオンライン開講。株式会社ISTL 代表取締役 礒部 晶 氏から、 半導体製造におけるPFASの使用状況と規制の影響 ~各国の規制動向と現状の対応、PFAS処理と代替材料開発動向ほか~ のテーマについて解説する講座です。
■本講座の注目ポイント
★有機フッ素化合物(PFAS)は優れた特性から幅広く利用され、半導体製造でも多くの工程に不可欠です。しかし一部PFASの有害性が認められ、規制が強化されています。本セミナーでは欧州REACHによる包括規制の最新動向を中心に、半導体産業への影響を解説します。さらにPFAS使用工程や目的、分析・処理技術、代替技術の進展、装置・材料・半導体メーカー各社の対応状況を整理し、今後の課題と展望を解説します。
★2026年2月24日WEBオンライン開講。【富山県立大学: 棚橋満氏】が、シリカフィラーのナノコンポジットに着目し、ポリマーの種類に合わせた分散性の均質化、界面制御、混合・混練技術や、表面改質を必要としない簡易調製法について解説します。
■本講座の注目ポイント
シリカフィラーは、樹脂の補強や機能付与を目的に、半導体封止材、放熱材料、接着、塗料など幅広い分野で用いられています。本講座ではナノコンポジットに着目し、ポリマーの種類に合わせた分散性の均質化、界面制御、混合・混練技術について解説します。また、表面改質を必要としない簡易調製法についても説明します。
★2026年2月24日 元凸版印刷 NPOサーキットネットワーク 理事 事務局長 大久保 利一先生が半導体基板におけるめっき技術の基礎と材料技術・課題、特にめっき浴管理やトラブル対策について、じっくり解説するまたとない講座です。
★トコトンやさしい半導体パッケージとプリント配線板の材料の本や、トコトンやさしい半導体パッケージ実装と高密度実装の本の編著者である大久保先生により講座!
★本セミナーでは、電解銅めっき、無電解銅めっき、無電解Ni/Auめっきの基礎を整理するとともに、めっき添加剤の作用機構、電流密度分布と膜厚均一化の考え方を解説し、現場で役立つ実務的な理解を提供する。
★2026年2月24日WEBでオンライン開講。 電気通信大学 新竹先生、東京科学大学 土方先生がそれぞれの立場で誘電エラストマーを用いた高分子アクチュエータ・E-Skin(電子人工皮膚)の開発とロボティクスへの応用・課題について解説する講座です。
■注目ポイント
★誘電エラストマーアクチュエータは、構造が単純で薄く軽量であり、応答性に優れ大きな変形を出力できるうえ、高い電気機械効率を有する、有望なソフトアクチュエータ技術!
★本講演では、誘電エラストマーアクチュエータの原理や特徴、主要な材料および製作・設計方法について説明するとともに、把持・操作デバイス、モバイルロボット、ウェアラブル・医療応用など、ロボティクスにおける多様な応用事例を紹介し、最新の研究動向と今後の展望についても述べる!
★2026年2月25日WEBオンライン開講。【東京大学: 藤原弘和氏】半導体メーカーでのデバイス開発経験を持つ講演者が、EUVリソグラフィ技術の原理や課題、レジスト材料について解説します。
■本講座の注目ポイント
当日にご参加できない方は録画視聴が可能です。(2/25~3/11)
本講演では、微細加工技術の基礎から始まり、フォトリソグラフィ技術の原理や特長、さらに最新のEUVリソグラフィ技術について、光と物質の相互作用に基づいて詳しく解説します。リソグラフィを学びたい方、レジスト材料開発に携わる方に向けた講座です。
★2026年2月26日実施。WEBでオンライン開講。東北大学 金属材料研究所 久保 百司 先生がニューラルネットワーク分子動力学法の基礎と応用:データ駆動型材料設計について解説する講座です。
★データ科学と計算科学を組み合わせた「ニューラルネットワーク分子動力学シミュレーション」が、大学などの研究機関のみならず、企業においても大きな注目を浴びている!
★①第一原理計算と同等の計算精度で大規模計算が可能、②パラメータ開発の困難さからの脱却が可能、③8元素種を越えるような多元素系への適用が可能、④複雑な化学反応への対応が可能、⑤二次元材料への応用が可能、などニューラルネットワーク分子動力学法はこれまでの分子動力学法に比較して多くの長所を有することから、その産業応用が加速度的に広がっている!この手法を学び、先進的な開発に活用する!
★2026年2月27日:会場&WEB開講【機能性カーボンフィラー研究会・副会長:前野氏】カーボンブラック・導電性炭素材料の専門家が素材ごとの特性と高導電化、最適分散技術について解説する講座です。
■本講座の注目ポイント
※こちらは会場開催となります(名刺交換&製本テキスト&お弁当付き!)
※WEB参加もご希望により対応します
導電性カーボンブラックは、電池やキャパシタなどのニューパワーソース分野から樹脂複合材・電子材料まで幅広く利用されています。本講演では、導電性カーボンブラックの構造・種類・導電機構の基礎から、分散や混練など導電性を左右する要因、さらに高機能化技術までを解説します。
★2026年2月27日WEBオンライン開講。【横浜国立大学:馬場氏】長年シリコンフォトニクス・光集積回路を研究している専門家が、基礎からファウンダリを活用した製作。最新の研究を解説する講座です。
■本講座の注目ポイント
シリコンフォトニクスは、データ通信・AI・センサ分野を支える光集積回路技術として急速に発展しています。本講演では、光導波路・アクティブデバイスの設計から最新の研究開発まで、講師の数多くのファウンダリ経験を経験に基づいて解説します。これからシリコンフォトニクスを活用したい研究者・技術者に向けた講座です。
★2026年2月27日WEBでオンライン開講。 株式会社荏原製作所 今井氏、株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 岩畑氏、三菱ケミカル株式会社 竹下氏がそれぞれの立場で半導体製造における洗浄プロセスの基礎・各工程に適した洗浄剤と新規応用展開について解説する講座です。
■注目ポイント
★半導体3D化、接合、において欠かせない洗浄プロセスに注目し、なぜ洗浄が重要なのか、どのような課題があるのかを分かりやすく整理!
★Wafer to Wafer と Die to Wafer の違いや特徴にも触れながら、先端パッケージング技術の洗浄の基礎的な考え方を解説!
★2026年2月27日WEBでオンライン開講。西包装専士事務所 西氏が、【資源有効利用促進法改正の最新動向と企業の対応】について解説する講座です。
■注目ポイント
★世界のリサイクルの現状、国際プラスチック条約、先行するEUのグリーンディール政策の現状、及び資源法改正の審議状況、日本のリサイクルの現状と課題、技術開発状況、企業の対応に関しご紹介!