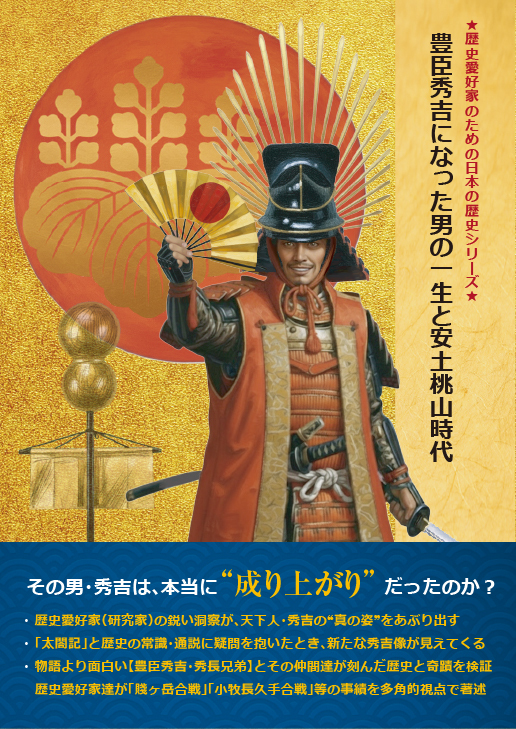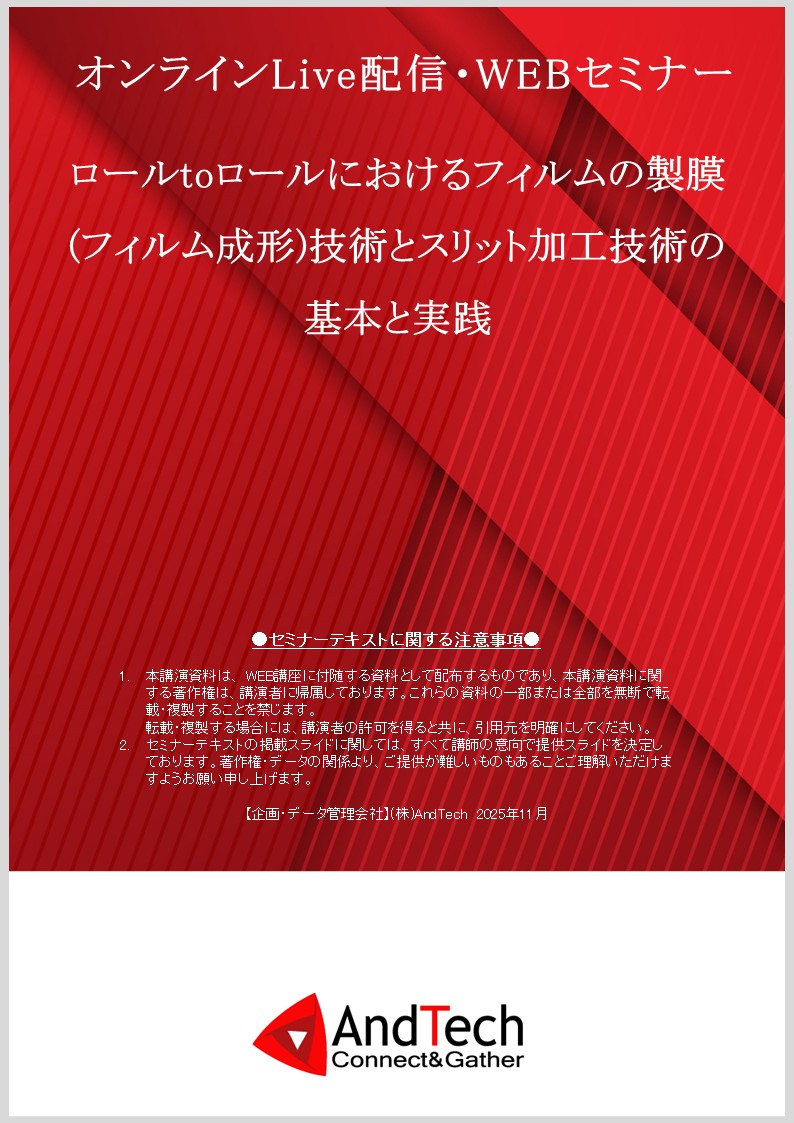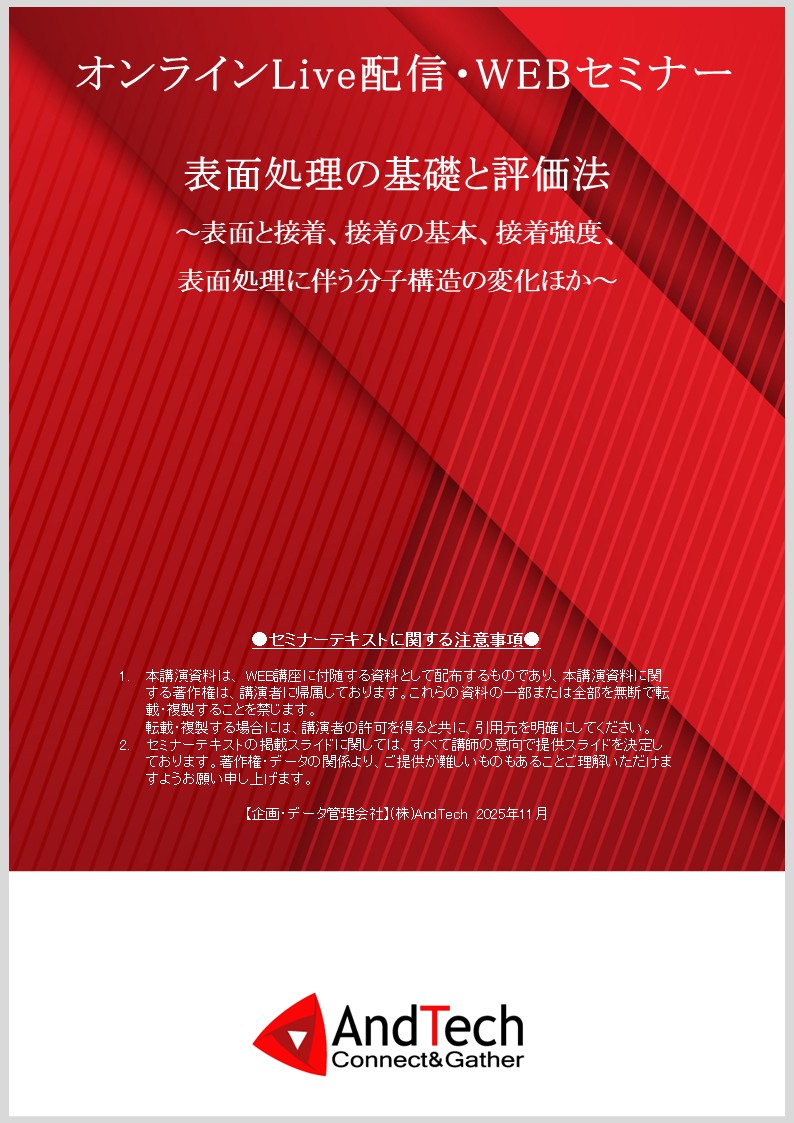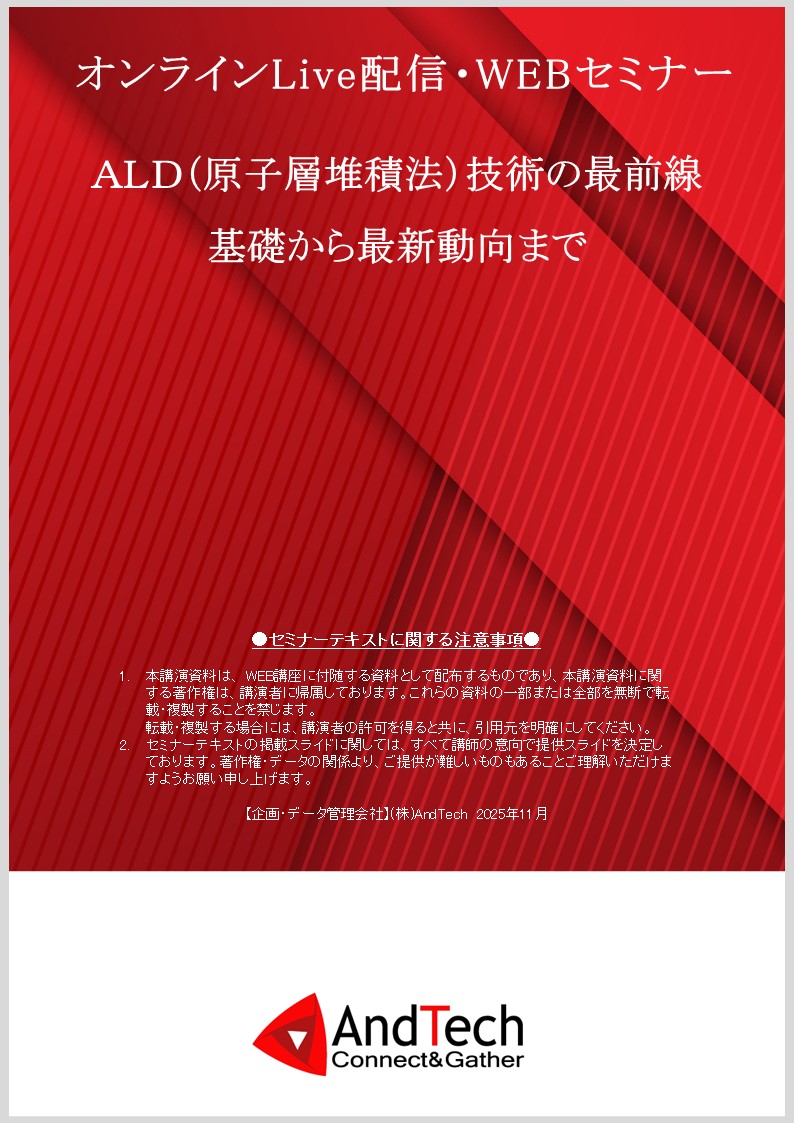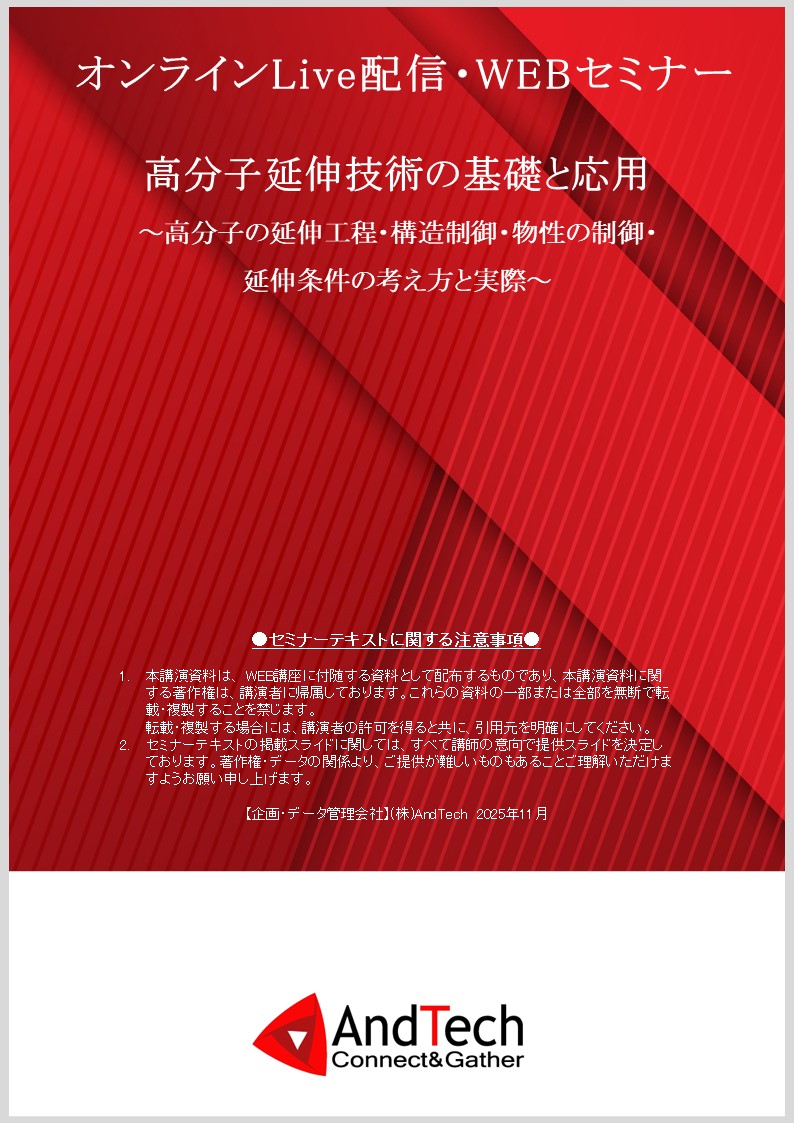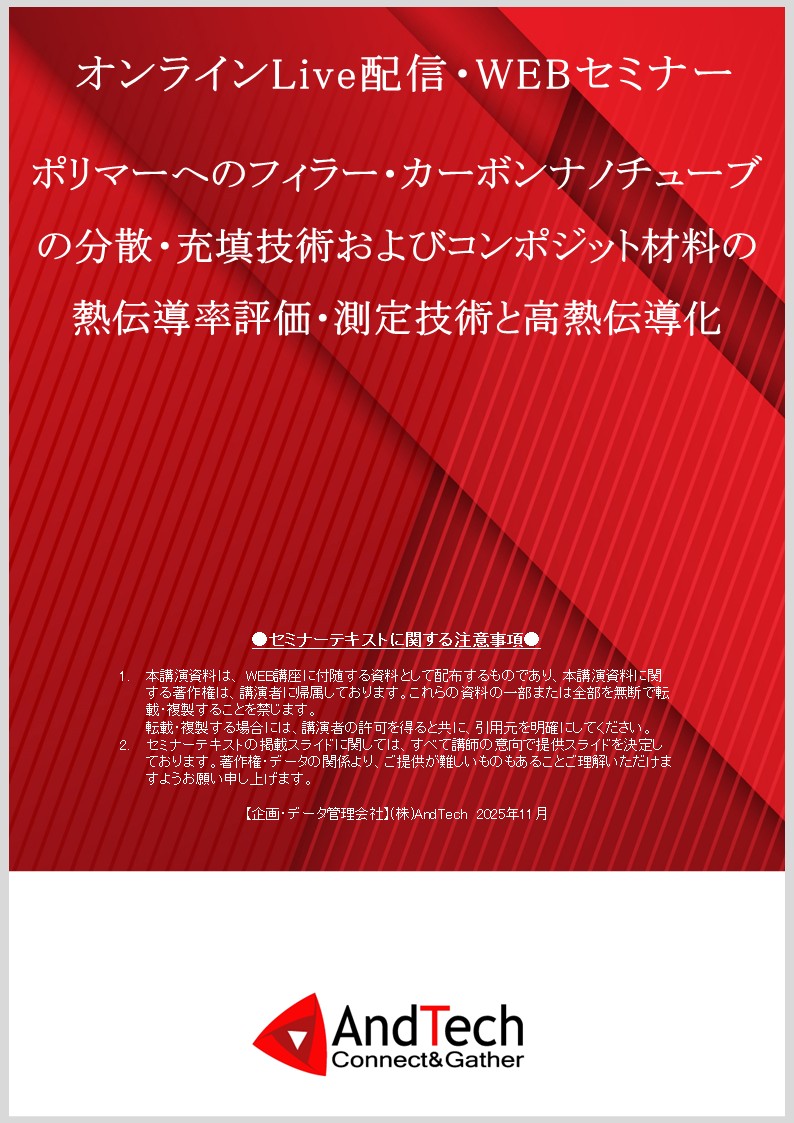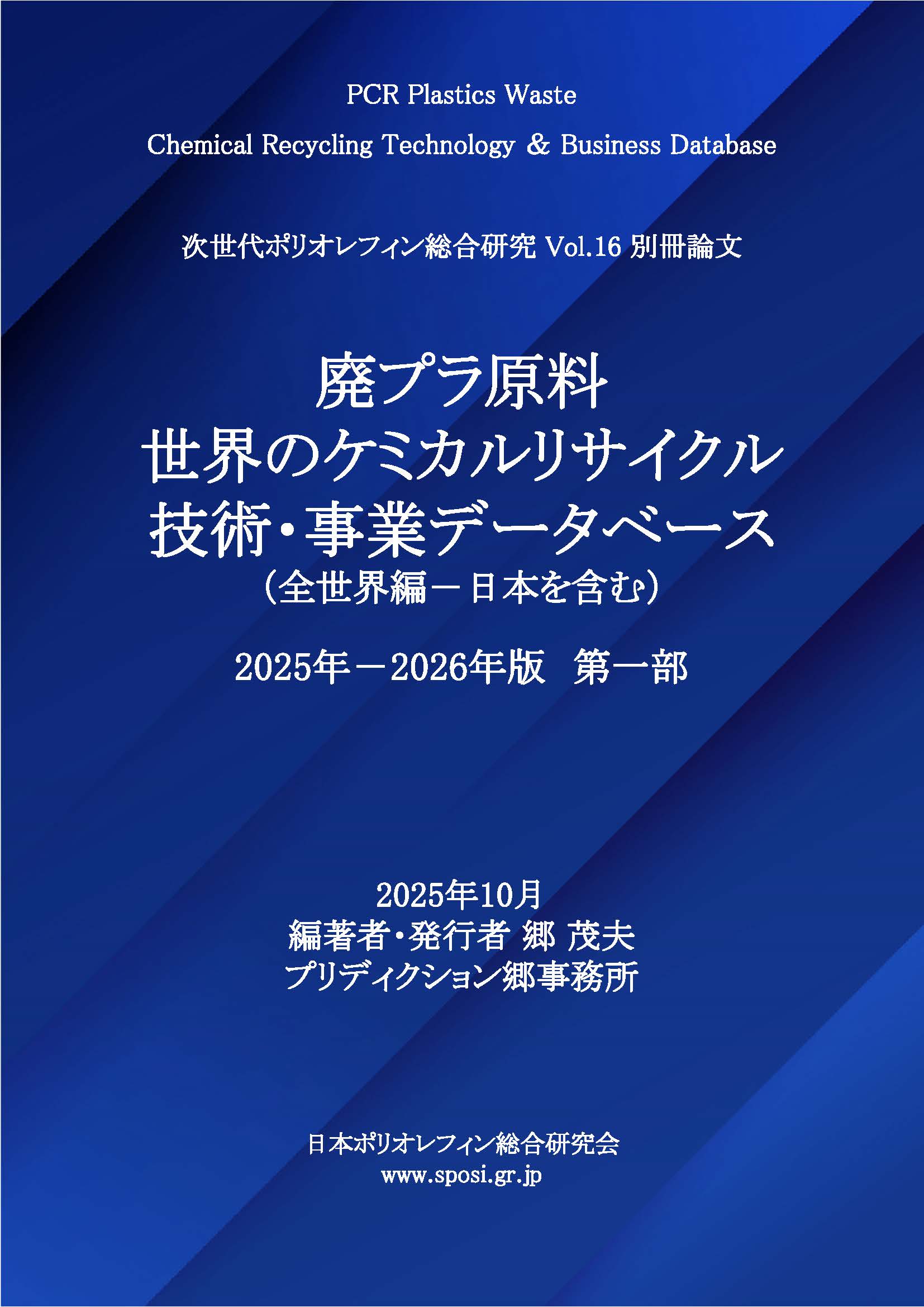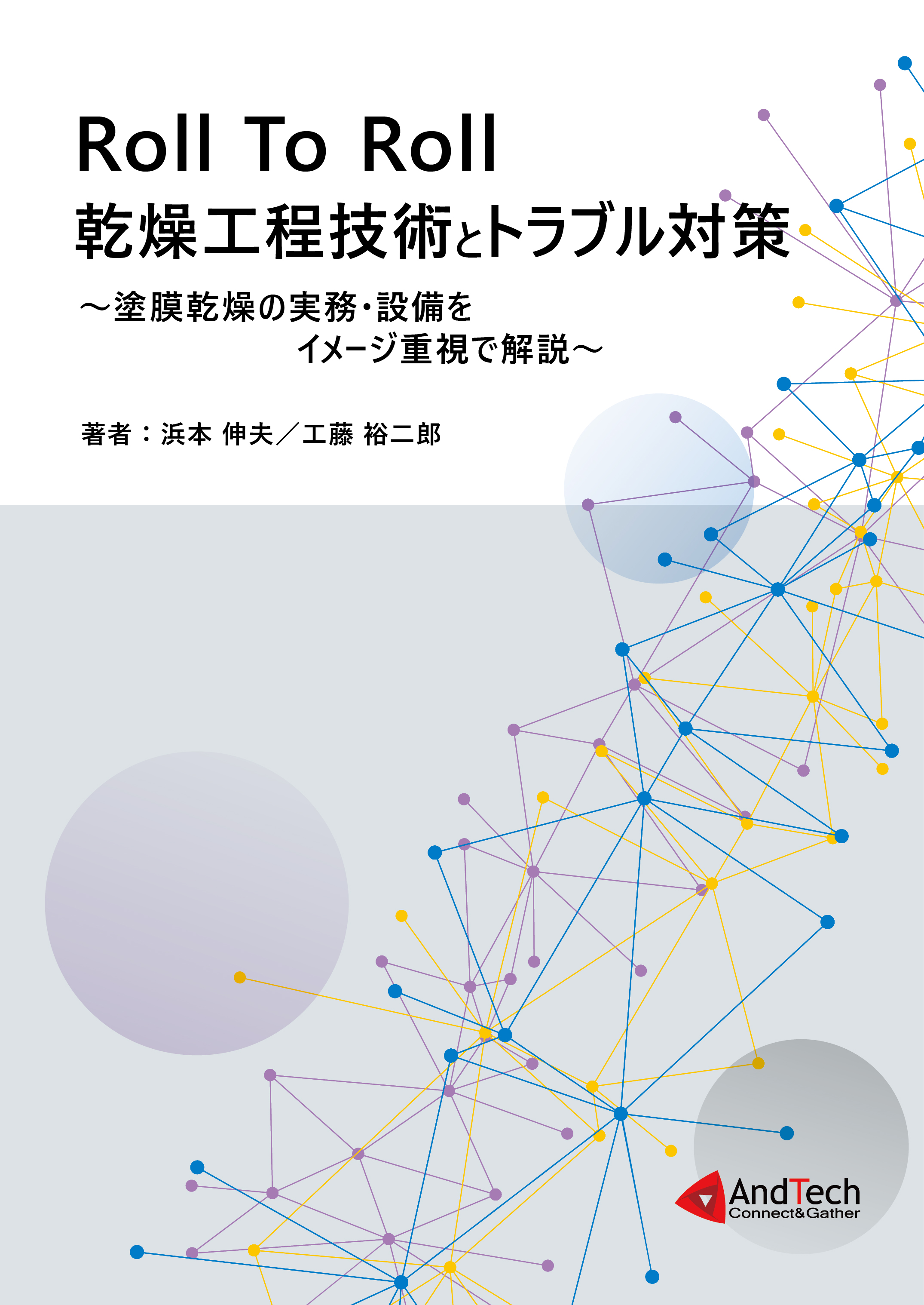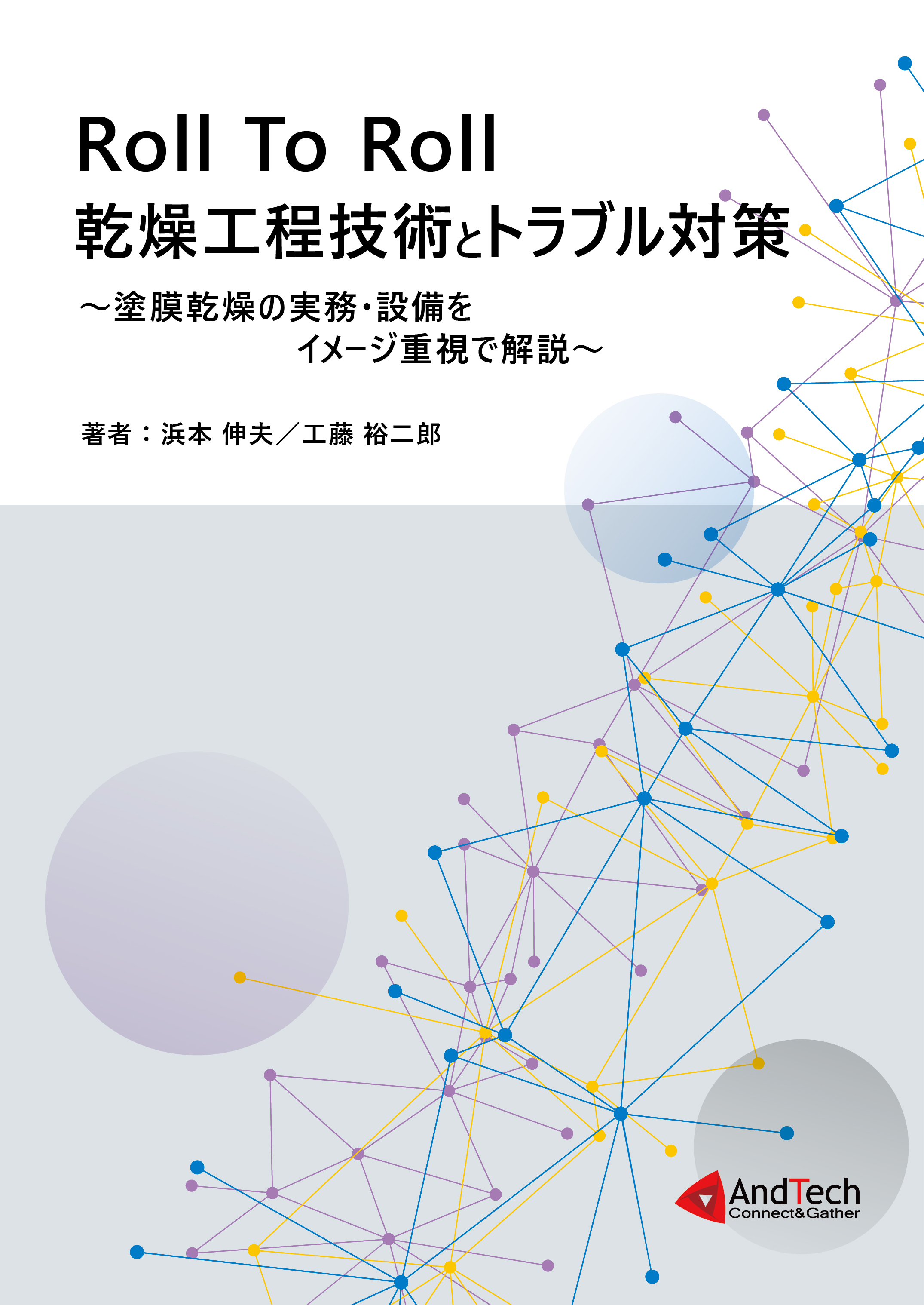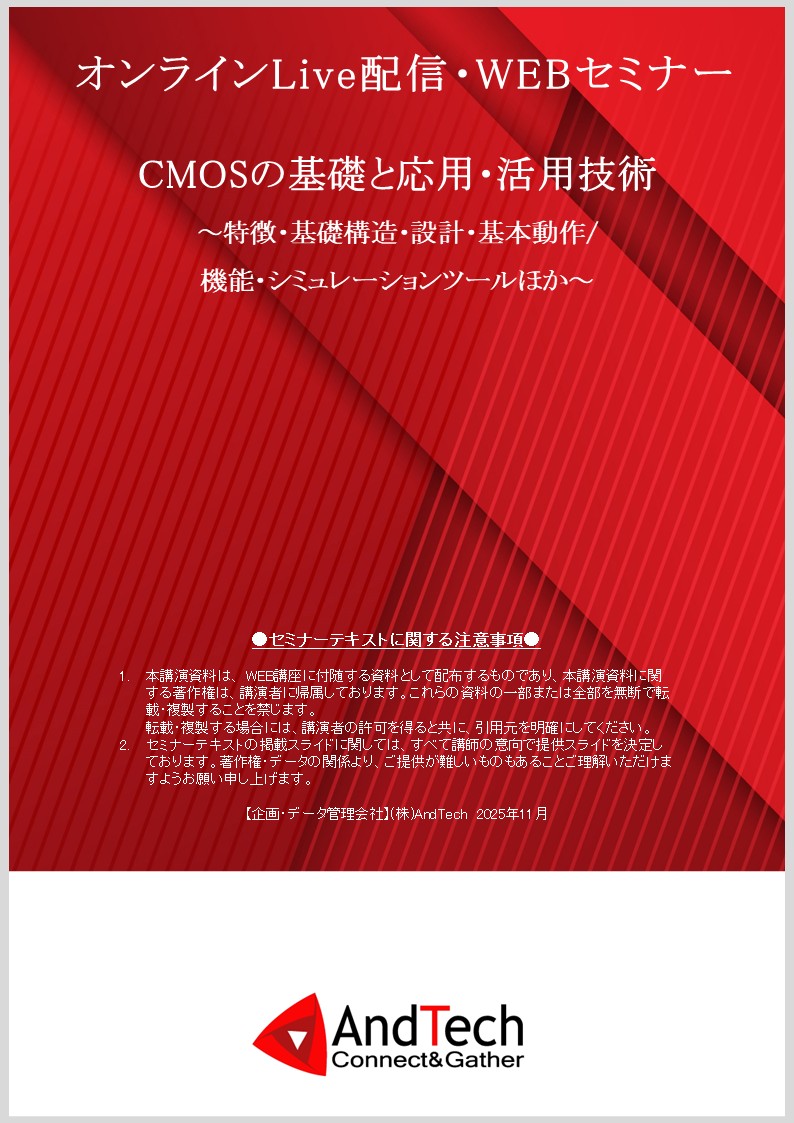書籍・セミナーテキスト 517 件中 381 ~ 390 件目
★その男・秀吉は、本当に❝成り上がり❞だったのか?
★歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ第2弾!
2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟」の豊臣秀吉の生涯(歴史)に焦点を当てた歴史論考集
★物語より面白い【豊臣秀吉・秀長兄弟】とその仲間達が残した歴史と奇蹟を辿る!
★「三度の飯より歴史」が大好きな歴史愛好家(バカ)達に送る通説に埋もれた「語られざる秀吉」に光を当てた一冊!
★秀吉の天下統一を支えた一門・家臣・越境人材の書き下ろし列伝風コラムも収録(61名)
■本テキストの主題および状況
★プラスチックフィルムは、電子、医療、食品など、ほとんど全ての産業で使用される不可欠な材料です。特に通信・エネルギー分野では、高耐久・高強度といった性能を満たす高機能フィルムの市場が拡大しています。
★ロールtoロールによるフィルムの製造は、効率的に量産する手段として注目され、光学、電子、電池分野などの、多種の用途に展開されつつあり、本テキストはこれを学ぶ絶好な機会となります。
★スリット加工とは、ロール状に巻かれたフィルムや紙などの素材を必要なサイズ幅にカットし、ロール状に巻き取っていく加工方法となります。
■注目ポイント
★フィルム製膜(成形)・スリッター設備・プロセスの技術ポイントとは!?
★フィルム製膜(成形)・スリッター工程における課題、発生する欠陥とその対策例を紹介!
★ロールtoロール製造における技術内容や課題とは!?
■本テキストの主題および状況
★プラスチックやゴムは単独使用が減り、複合材料としての接着性が重要になっている。多くの材料はそのままでは接着力が弱く、表面処理による改質が必要となる。表面処理には物理的方法と化学的方法があり、それぞれに長所と短所がある。それらの処理法の選定は材料特性を理解した技術者が行うべきである。本テキストの最大のポイントは接着とはどういう現象であるかを理解することであり、高分材料の専門家の立場から解説します。
■注目ポイント
★表面と接着について学習、習得できる!
★接着の基本について学習、習得できる!
★接着強度について学習、習得できる!
★表面処理について学習、習得できる!
★表面処理に伴う分子構造の変化について学習、習得できる!
★表面処理後のキャラクタリゼーションについて学習、習得できる!
★これらの実例について学習、習得できる!
■本テキストの主題および状況(執筆者より)
★ALD(原子層堆積)法は、原子層サイクルで膜厚・組成を精密制御し、3次元立体構造等にも均一被覆できる技術です。
★ゲート絶縁膜、キャパシタ、配線バリア層に加え、コーティングなど多分野で実用化が進んでいます。
★供給→パージ→反応→パージ各工程は、吸着・表面反応といった速度論に支配され、最適化には体系理解が必須です。
■注目ポイント
★理想特性(自己終端反応、面内・深さ方向の均一性、ALD Window)を実現するための着目点と進め方を解説!
★選択成長(ASD)の原理と開発方針に触れ、関連学会の最新動向も概説!
★ALDをすぐに使えるようにするためのQCMなどのその場観察手法についても解説!
■本テキストの主題および状況
★フィルムや繊維は引張には強く、圧縮にはしなやかに曲がるという特有の性質を示す。相反するこれらの性質は、延伸によって形成される構造によってもたらされる。その原理と延伸条件による物性制御の基礎について解説する。
■注目ポイント
★高分子の延伸工程、延伸装置と延伸条件延伸工程で加わる力と熱、延伸の基礎方程式等について学習、習得できる!
★延伸による構造制御、分子配向の3要素、延伸による分子配向等について学習、習得できる!
★延伸による物性制御、屈折率と複屈折制御、力学物性制御等について学習、習得できる!
★光学的性質と構造との関連性、力学的性質と構造との関連性等について学習、習得できる!
■本テキストの主題および状況(執筆者より)
★従来、コンポジット材料の熱伝導率の向上は、フィラーの最密充填構造形成により実現されてきました。
★近年、コンポジット材料の熱伝導率を格段に向上させる手法として、フィラーのハイブリッド化による伝熱ネットワーク構造形成技術が注目されており、従来のフィラーとナノフィラーの組み合わせは、有効な手段であると考えられます。
■注目ポイント
★従来のフィラーとカーボンナノチューブのポリマーへの分散・充填技術、表面処理技術とコンポジット材料の熱伝導率評価技術について解説!
★従来のフィラーとナノフィラーを活用したコンポジット材料の高熱伝導化事例を紹介!
★コンポジット材料の熱伝導率測定方法の課題とは!?
本誌は,日本ポリオレフィン総合研究会会誌「次世代ポリオレフィン総合研究 Vol。16」の第4部「統計と調査」に属する論文記事を,データ量が多いため,別冊(PDF版,ネット閲覧書籍)という形で発行するものです。
別冊ではありますが,研究会会誌 Vol。16 に採択された調査・研究論文です。その内容は,現在の大きな環境問題の1つである「廃棄プラスチックのリサイクル」に関するもので,特に「ケミカル・リサイクル」に関わる調査です。
★(こちらは電子書籍版となります)。本書はRoll to Roll工程に関わる方々の課題遂行をサポートするための参考書
★ 「機能性フィルムにおける基礎・最新動向とスロット塗工技術」、「Roll to Roll塗工技術とスケールアップ」に続く第3弾!!
★ 機能性フィルムやLIB電池電極、ペロブスカイトPVなどの応用事例を含めた事例も紹介する
★ 化学系出身で塗工開発/フィルム製造の現場を見てきた浜本氏と、機械系出身で乾燥設備の設計・開発を行ってきた工藤氏から、それぞれの視点で乾燥工程を多角的に記載した、実務に役立てるための意欲的な一冊となっています!
★(紙限定版の購入サイトになります)本書はRoll to Roll工程に関わる方々の課題遂行をサポートするための参考書
★ 「機能性フィルムにおける基礎・最新動向とスロット塗工技術」、「Roll to Roll塗工技術とスケールアップ」に続く第3弾!!
★ 機能性フィルムやLIB電池電極、ペロブスカイトPVなどの応用事例を含めた事例も紹介する
★ 化学系出身で塗工開発/フィルム製造の現場を見てきた浜本氏と、機械系出身で乾燥設備の設計・開発を行ってきた工藤氏から、それぞれの視点で乾燥工程を多角的に記載した、実務に役立てるための意欲的な一冊となっています!
■本セミナーの主題および状況
★半導体産業の中で最も需要が大きく、技術的な進化を遂げ、人類の発展に大きく影響するCMOSデバイスの基礎をじっくりと学びましょう。本テキストではCMOSデバイスの技術的な解説に留まらず、これを用いた応用回路やアプリケーションについても紹介します。 生成AIによって、半導体設計は誰でもできるようになるかもしれません。その基本となるCMOSデバイスの基礎を学び、技術革新をもたらす半導体設計者になりましょう。
■注目ポイント
★半導体の歴史・分類について学習、習得できる!
★CMOSの特徴・基本構造等について学習、習得できる!
★CMOSの特性・故障モードについて学習、習得できる!
★ASIC, SoCについて学習、習得できる!
★設計・シミュレーションツールについて学習、習得できる!
★半導体使いこなしの術、前工程・後工程について学習、習得できる!
★今後の未来動向について学習、習得できる!